登場人物

ルポライター 鷺沼探偵
フリーのルポライター。三流雑誌の依頼で曰く付きの物件を取材する日々を送る。生活は楽ではない様子が窺える。

不動産屋「業深」社長 黒田
太った体に安物のスーツを着こなし、常に人を食ったような笑みを浮かべている。目は獲物を探す蛇のように光っており、悪徳な雰囲気を漂わせている。
悪徳不動産屋との再会
三流雑誌のライター、鷺沼探偵の生活は、常に薄氷の上を歩むようだった。わずかな原稿料をかき集め、どうにか糊口をしのぐ日々。
そんな彼の元には、今日もまた、ろくでもない依頼が舞い込んできた。

鷺沼さん、相変わらず貧乏暇なし、って顔してますねえ、ケケケ…
事務所に現れたのは、悪徳不動産屋としてその名を知られる「業深(ごうふかし)」の社長、黒田だった。太った体に安物のスーツが食い込み、常に人を食ったような笑みを浮かべている。その奥で、獲物を探す蛇のような鋭い光を宿した目が、鷺沼を値踏みするように見つめていた。

また何か、曰く付きの物件ですか?」
鷺沼はうんざりとした声で問い返した。黒田が持ち込んでくるのは、幽霊が出るとか、過去に凄惨な事件があったとか、まともな人間なら絶対に手を出さないような物件ばかりだ。
それを取材し、記事にするのが鷺沼の仕事だった。

ええ、ええ、今回もとびきりですよ。なんでも、数年前に閉鎖された遊園地なんですけどねえ…『ドリームランド』。出るらしいんですよ、盛大に
黒田はニヤつきながら、古びたパンフレットを鷺沼の前に差し出した。

色褪せた表紙には、かつては夢と希望に満ち溢れていたであろう遊園地の賑やかなイラストが描かれていた。しかし、今の鷺沼には、それがどこか物悲しく、嘲笑っているようにすら見えた。

夜になると子供たちの嬌声が聞こえるとか、動かないはずのメリーゴーランドが勝手に回るとか…。まあ、噂ですけどね、ケケケ。鷺沼さんみたいな変わり者には、最高のネタでしょう?
黒田の言葉には、いつも人を小馬鹿にするような響きがあった。彼にとって鷺沼は、危険な場所に平気で足を踏み入れ、ろくでもない噂を記事にしてくれる、都合の良い存在でしかないのだろう。

原稿料は、いつも通り、雀の涙ほどでしょうね・・・・。
鷺沼は自嘲気味に言った。

まあまあ、そんなこと言わずに。売れっ子ルポライターへの第一歩ですよ!ケケケ…
黒田は肩をすくめて笑った。
鷺沼はため息をついた。断るという選択肢は、彼にはほとんど残されていない。
わずかな原稿料でも、生活のためには受け入れざるを得なかった。
こうして、彼は再び、黒田の差し出す危険な舞台へと足を踏み入れることになった。
今回の舞台は、「ドリームランド」という名の、寂れた遊園地だった。
忘れ去られた楽園の残滓
翌日、鷺沼は黒田から渡された簡単な地図を頼りに、「ドリームランド」へと向かった。
郊外の寂れた場所にひっそりと佇むその遊園地は、既にその名前から想像されるような夢や希望の輝きを失い、ただの陰鬱な廃墟と化していた。
錆び付いたゲートが、風に吹かれるたびに寂しげな音を立てている。かつては多くの家族連れや若者たちで賑わったであろう入り口は、今は蔦が絡まり、荒れ果てた姿を晒していた。
場内に入ると、折れた看板、色褪せたキャラクターのオブジェ、そして朽ち果てたアトラクションの残骸が、まるで忘れ去られた玩具のように散乱している。
最初に鷺沼の目に飛び込んできたのは、遊園地のシンボルだったはずの巨大な観覧車だった。いくつかのゴンドラは落下し、見るも無残な姿を晒している。
風が吹くたびに、金属同士が擦れ合うような、耳障りな音が響き渡り、まるで観覧車そのものが悲鳴を上げているようだった。
次に足を運んだのは、かつて子供たちの歓声が響き渡っていたであろうメリーゴーランドだった。木馬たちは色褪せ、目は虚ろで、今にも朽ち果てそうだ。
黒田が言っていた「夜になると回る」という不気味な噂を思い出すと、背筋に冷たいものが走った。想像力を掻き立てられる廃墟の雰囲気は、確かに幽霊の噂に信憑性を与えているようだった。
さらに奥へと進むと、ジェットコースターの乗り場へと向かった。レールは錆び付き、あちこちで歪んでいる。かつてはスリルと絶叫を生み出していたであろう乗り物は、今はただの鉄の塊と化し、空に向かって寂しく伸びている。
もし、このジェットコースターが夜中に動き出したら…。想像するだけで、身の毛がよだった。
恐怖の館に潜む影
お化け屋敷の中は、昼間だというのに外界の光を一切遮断し、 闇が支配していた。
懐中電灯の光だけが頼りだったが、その光もまた、目の前のわずかな範囲しか照らし出すことができない。足元には何かが散乱しており、歩くたびに「カサカサ」「ゴツゴツ」といった不気味な音が響き、鷺沼の神経を逆撫でした。
壁には、かつては鮮やかだったであろうおどろおどろしい絵が、色褪せ、剥がれ落ちた状態で残っている。首のない騎士、血まみれのゾンビ、歪んだ笑顔のピエロ…。
それらは、現役の頃には子供たちを怖がらせ、楽しませたのだろうが、今の暗闇の中では、ただただ不気味な存在感を放っていた。
懐中電灯の光が捉えたのは、床に転がる首がもげたマネキンの頭だった。虚ろな目が、まるで鷺沼を見つめているように感じられ、彼は思わず息を呑んだ。さらに奥へ進むと、天井から破れた蜘蛛の巣が垂れ下がり、何かに引っかかって揺れている。その先に目をやると、色褪せた血糊のようなものが付着した、鋭利な刃物のおもちゃが落ちていた。
かつてこの場所は、作り物とはいえ、人々に恐怖と興奮を与えていたのだろう。しかし今、残されているのは、時の流れに取り残された、ただの陰惨な残骸だった。
その静けさの中に、過去の喧騒や人々の感情が閉じ込められているような気がして、鷺沼は背筋がゾッとした。
お化け屋敷の奥へと進むにつれて、空気はますます重く、湿っぽくなってきた。カビ臭さに混じって、微かに鉄錆のような、あるいはもっと生臭いような、不快な匂いが鼻をつく。
それは、単なる廃墟の匂いではないような気がして、鷺沼の心臓はドキドキと高鳴ってきた。
ふと、背後で微かな物音がしたような気がした。振り返ってみたが、そこには何もいない。しかし、確かに何か気配がした。暗闇の中で、何かが蠢いているような、そんな錯覚に襲われた。

まさか…本当に何かいるのか?
鷺沼は小さく呟いた。理性では否定しようとするものの、廃墟の異様な雰囲気と、黒田の不気味な言葉が、彼の心をじわじわと不安で満たしていく。
懐中電灯を持つ手が、わずかに震えていることに気づいた。
お化け屋敷を抜け出し、外の光を浴びた時、鷺沼は安堵のため息をついた。しかし、彼の心に残ったのは、拭いきれない不気味な感覚だった。
あの暗闇の中で感じた、得体の知れない気配。それは、単なる気のせいだったのだろうか。
静寂を切り裂く鉄の咆哮
お化け屋敷のじめじめとした空気を払い落とすように、鷺沼は大きく息を吸い込んだ。
次に目指したのは、ジェットコースターの乗り場だった。錆び付いたレールは、複雑に絡み合いながら空へと伸び、その頂点で途切れている。
かつては多くの人々を乗せ、スリルと絶叫を生み出していたであろうその乗り物は、今はただの巨大な鉄のオブジェと化し、寂しげなシルエットを空に描いていた。
乗り場へと続く階段は、所々朽ちており、足を踏み入れるたびにギシギシと音を立てた。柵は錆び付き、今にも崩れ落ちそうだ。
鷺沼は慎重に足を進め、乗り場へと辿り着いた。そこには、色褪せたシートが並び、安全バーは固く閉ざされたまま、動くことは二度とないだろうことを静かに物語っていた。
ジェットコースターのレールを見上げていると、強風が吹き抜け、錆び付いた鉄骨がきしむ音が、まるで遠吠えのように聞こえた。その音は、かつての絶叫を吸い込んだまま、静かに朽ち果てていくジェットコースターの、悲痛な叫びのようにも聞こえた。

夜になると、このジェットコースターが勝手に動き出すという噂もある
と黒田は言っていた。そんな馬鹿な、と鷺沼は思ったが、この荒廃した光景を前にすると、ありえないことではないような気もしてくる。
もし本当に、夜の闇の中でこの巨大な鉄の塊が動き出したとしたら…。想像するだけで、全身の毛が逆立った。
遊園地内を一通り歩き回り、写真撮影を終えた鷺沼は、当時の資料や記録が残っていないかと、管理事務所らしき建物を探すことにした。
しかし、見つかった建物はどこも窓ガラスが割れ、壁には落書きがされ、内部はゴミや埃で埋め尽くされていた。時の流れは、この場所からあらゆる活気を奪い去り、ただの抜け殻のような姿に変えてしまっていた。
諦めかけていたその時、鷺沼はひときわ朽ち果てたプレハブ小屋を見つけた。ドアは半開きになっており、中を覗くと、埃を被った段ボール箱がいくつか積まれていた。もしかしたら、この中に何か手がかりがあるかもしれない。
鷺沼は、最後の望みを託して、その小屋へと足を踏み入れた。
埃に埋もれた真実の断片
プレハブ小屋のドアを押し開けると、むせ返るような埃の臭いが鼻を突いた。
長らく人の手が触れられていないことが、その匂いだけで理解できた。
内部は薄暗く、窓ガラスは汚れでほとんど外の光を通さない。懐中電灯の光を頼りにあたりを見回すと、積まれた段ボール箱の他にも、古びた事務机や椅子などが放置されているのが見えた。
鷺沼は、埃を被った段ボール箱の一つに近づき、慎重に蓋を開けた。中には、色褪せたパンフレットやポスター、従業員の名簿、そして何冊かのノートのようなものが入っていた。それは、閉鎖された遊園地の、忘れ去られた記憶の断片だった。
ノートを手に取り、パラパラとページをめくっていくと、それは当時の業務日誌であることがわかった。日付は、遊園地が閉鎖される数ヶ月前から、閉鎖直後までのものが記録されていた。
鷺沼は、閉園間際の記述の中に、何か手がかりになるような情報がないかと、目を凝らして読み進めていった。
すると、ある日の記述に、気になる内容が書かれていた。
「最近、夜になると遊園地内で奇妙な音がするという報告が相次いでいる」
「誰もいないはずのアトラクションが、勝手に動いているのを見たという警備員の証言」
「原因不明の事故が頻発し、従業員の間で不気味な噂が広まっている」…。
鷺沼は息を呑んだ。黒田が言っていた噂は、単なる作り話ではなかったのかもしれない。業務日誌には、遊園地内で実際に起こっていた異変が記録されていたのだ。
さらに読み進めていくと、別の日の日誌に、手書きで大きく「呪い」という文字が書かれているのを見つけた。その周りには、意味不明な記号や絵が、まるで子供の落書きのように描かれており、異様な雰囲気を醸し出していた。
その筆跡は、他の業務的な記述とは明らかに異質で、強い感情が込められているように感じられた。
鷺沼は、この日誌こそが、ドリームランドの幽霊騒動の真相に繋がる鍵なのではないかと直感した。閉園の理由は、単なる経営不振だけではなかったのかもしれない。
もしかしたら、この遊園地には、何か恐ろしい秘密が隠されているのではないか。
呪いの文字、増殖する悪夢
「呪い」という不吉な文字が書かれたページを、鷺沼は食い入るように見つめた。その周りに描かれた奇妙な記号は、まるで古代文字のようにも見えたが、どこか稚拙で、歪んでいた。
それは、強い恐怖や不安に駆られた人間が、藁にも縋る思いで書きなぐったもののように感じられた。
日誌の他のページにも、断片的に不気味な出来事の記述が見られた。
「メリーゴーランドの音楽が、誰もいないのに夜中に聞こえる」
「お化け屋敷の中で、子供のすすり泣く声がする」
「ジェットコースターの安全バーが、突然ガシャンと音を立てて閉まった」
「従業員が、誰もいないはずの倉庫で、複数の子供たちが遊んでいるのを見たと言い出した」
これらの記述は、単なる噂や気のせいでは済まされない、異様な雰囲気を醸し出していた。
閉園間際に、この遊園地では一体何が起こっていたのだろうか?そして、その「呪い」とは、一体何を意味するのだろうか?
鷺沼は、さらに日誌を読み進めていった。すると、数日後のページに、より具体的な記述が見つかった。
「先日、小さな女の子が、メリーゴーランドの近くで行方不明になった。警察も捜索しているが見つからない」
「その子の母親が、毎晩のように遊園地に現れては、娘の名前を叫んでいる」
「原因不明の機械の故障が頻発し、ついに死傷者を出す事故が起きてしまった」…。
鷺沼は息を呑んだ。行方不明の女の子、そして死亡事故。もしかしたら、この遊園地の閉鎖には、単なる経営不振以上の、もっと悲惨な理由が隠されているのかもしれない。
そして、「呪い」という言葉は、そうした不幸な出来事と何か関係があるのだろうか?
その時、背後でカタッという小さな音が聞こえた。鷺沼は反射的に振り返ったが、そこには誰もいない。
しかし、確かに何かが動いたような気がした。プレハブ小屋の古びた木材が、軋んだのかもしれない。そう思おうとしたが、心臓の鼓動は早くなっていた。
再び日誌に目を戻すと、最後の数ページには、さらに不穏な言葉が並んでいた。
「もう、おかしい。何かがいる」
「あの子供たちの声が、毎晩聞こえる」
「誰も信じてくれない」
「このままでは、みんな狂ってしまう」
「呪いだ…きっと、呪いだ…」
そして、最後の日付のページには、震えるような筆跡で、たった一言だけ書かれていた。
「ごめんなさい…」
鷺沼は、背筋に氷のような冷たさが走るのを感じた。この日誌を書いた人物は、一体何に謝っていたのだろうか?
そして、この遊園地で起こった悲劇の真相とは、一体何なのだろうか?
その時、プレハブ小屋の外から、かすかに、しかし確かに、子供たちの嬌声のようなものが聞こえてきたような気がした。
それは、楽しそうな笑い声ではなく、どこか悲しげで、恨めしそうな、そんな声だった。
閉ざされた空間、侵食する恐怖
背後の音、そして聞こえてきた子供たちの声。それらは、鷺沼の理性では説明できない、不気味な現実として彼の心に突き刺さった。
彼は慌てて振り返ったが、プレハブ小屋の中には、先ほどから何も変わった様子はなかった。
しかし、確かに何かがおかしい。空気は重く、先ほどまで感じなかった、冷たい、まとわりつくような感覚が全身を覆っていた。
再び外の様子を窺おうと、入り口のドアに手をかけた。しかし、なぜかドアは固く閉ざされていて、びくともしない。
強く押しても、引いても、ドアはまるで何かに押されているかのように、開く気配を見せなかった。
閉じ込められた…!
焦燥感が、じわじわと鷺沼の心を蝕んでいく。外はまだ昼間のはずなのに、プレハブ小屋の中は、先ほどよりも明らかに暗くなっていた。窓ガラスの汚れのせいだけではないような、そんな気がした。
まるで、この空間だけが、外界から切り離され、異質な時間の中に閉じ込められてしまったかのようだった。
そして、聞こえてくる子供たちの声も、だんだんと大きさを増していく。それは、単なる幻聴ではない。確かに、すぐそこで、複数の子供たちが何かを囁き合っているのだ。
「あそぼう…」
「いっしょに…」
声は、最初は小さく、遠くから聞こえてくるようだったが、次第に近づき、まるで鷺沼の耳元で囁いているかのように感じられた。それは、楽しそうな誘いかけではなく、どこか切実で、執拗な、そんな響きを含んでいた。
鷺沼は恐怖で体が震え、一歩も動けなかった。このプレハブ小屋の中で、一体何が起こっているのか?
この声の主は、一体何者なのか?
懐中電灯の光を頼りに、周囲を照らしてみたが、そこには段ボール箱と古びた家具があるだけで、人影は見当たらなかった。
しかし、声は確かに存在する。それは、この小屋の壁の向こうから、あるいは床の下から、あるいは天井の上から、あらゆる方向から聞こえてくるようだった。
「かえして…」
「わたしの…」
子供たちの声は、次第にその内容を伴い始めた。それは、何かを探し求め、何かを訴えかけるような、悲痛な叫びだった。その声を聞いていると、鷺沼の胸にも、言いようのない悲しみが押し寄せてきた。
彷徨う魂の叫び
プレハブ小屋の中は、ますます暗くなってきた。外の光はほとんど届かず、懐中電灯の頼りない光だけが、わずかな範囲を照らし出す。
その光の中で、積まれた段ボール箱や放置された家具の影が、不気味な形を作り出し、まるで生き物のように蠢いているように見えた。
子供たちの声は、もはや囁き声ではなく、はっきりと耳に届くようになっていた。
「あそぼう」「いっしょに」という誘いの言葉は、次第に焦燥感を帯び、まるで懇願しているようだった。「かえして」「わたしの」という訴えは、悲痛さを増し、聞いているだけで胸が締め付けられるようだった。
鷺沼は、恐怖で喉がカラカラに乾き、呼吸をするのも苦しくなっていた。彼は、この声の主から逃れたい、この空間から一刻も早く脱出したいと強く思ったが、ドアは依然として固く閉ざされたままだった。
その時、段ボール箱の中から、何かがカタッと音を立てて転がり落ちた。鷺沼は、震える手で懐中電灯をその方向に向けた。
光が捉えたのは、古びたブリキの人形だった。目は大きく見開かれ、その小さな顔には、不気味な笑みが張り付いている。長い間放置されていたのだろう、表面は埃で薄汚れていたが、その異様な存在感は、暗闇の中でも際立っていた。
その人形を拾い上げた瞬間、鷺沼の頭の中に、まるで走馬灯のように、断片的な映像が流れ込んできた。楽しそうに遊ぶ子供たちの笑顔。鮮やかな色の遊具。賑やかな音楽。
しかし、その映像は突然途切れ、次の瞬間には、けたたましい悲鳴、泣き叫ぶ親たちの姿、そして、地面に倒れ伏し、血に染まったブリキの人形が映し出された。
鷺沼はハッとした。もしかしたら、この遊園地で、過去に子供たちの事故があったのではないか?そして、今聞こえてくる子供たちの声は、その事故で亡くなった子供たちの霊なのか?
そして、このブリキの人形は、その子供たちの、大切なものだったのではないか?
聞こえてくる声は、ますます切実さを増していく。
「かえして…」「わたしの…」
鷺沼は、その声が、まるで自分の手の中の人形に向かって言われているような気がした。その小さな人形に、子供たちの悲しみや無念の思いが、凝縮されているように感じられた。
人形の記憶、悲劇の断片
手の中のブリキ人形は、ひんやりと冷たく、どこか生気のない感触だった。しかし、その小さな体に、この遊園地で起きた悲劇の記憶が宿っているような気がして、鷺沼は強く握りしめることができなかった。
頭の中に流れ込んできた断片的な映像は、次第にその鮮明さを増していった。楽しそうにメリーゴーランドに乗る小さな女の子。その手には、まさしく今、鷺沼が手にしているのと同じようなブリキの人形が握られている。母親らしき女性が、優しい笑顔で見守っている。
しかし、次の瞬間、時空は歪み、けたたましい悲鳴が響き渡る。メリーゴーランドが異常な速度で回転し始め、遠心力で子供たちが次々と振り落とされる。地面に叩きつけられ、泣き叫ぶ子供たち。
そして、その中に、先ほどの女の子の姿もあった。彼女の手から離れ、地面に落ちたブリキ人形は、無残にも踏みつけられ、血のような赤い液体が滲み出ている…。
別の映像では、ジェットコースターが急停止し、乗客たちが激しく衝突している。救急隊員たちが駆けつけ、負傷者を運び出す騒ぎの中、小さな男の子が、壊れたブリキの人形を抱きしめながら、呆然と立ち尽くしている。
その人形は、先ほど鷺沼が見たものと、明らかに同じものだった。
これらの映像は、過去にこの遊園地で、複数の子供たちが巻き込まれる悲惨な事故が起こったことを示唆していた。
そして、今、このプレハブ小屋に響いている子供たちの声は、その事故で亡くなった子供たちの霊であり、彼らは、自分たちの失われた大切なもの、このブリキの人形を探し求めているのではないか。
「かえして…」「わたしの…」
声は、もはや悲痛な叫びとなっていた。鷺沼は、その声に応えなければならないと感じた。
彼らにとって、このブリキの人形は、失われた命の象徴であり、未だ癒えることのない悲しみの拠り所なのかもしれない。
鎮魂の祈り、かすかな光
鷺沼は意を決して、手にしていたブリキ人形を、そっと元の段ボール箱に戻した。そして、その箱に向かって両手を合わせ、心の中で静かに語りかけた。
「ごめんなさい。あなたたちの身に起こった悲しい出来事を、今知りました。あなたたちの悲しみは、きっと癒えることはないでしょう。でも、どうか、もう苦しまないでください。安らかに眠ってください」
言葉を発している間、鷺沼の心には、深い悲しみと、そして僅かながら、彼らに安らかな眠りを与えたいという願いが湧き上がってきた。
すると、不思議なことに、周囲を覆っていた重く冷たい感覚が、少しずつ薄れていくのを感じた。
耳元で響いていた子供たちの声も、次第に遠ざかっていくようだ。そして、固く閉ざされていたプレハブ小屋のドアが、ゆっくりと、まるで何かに導かれるように、カタッと音を立てて開いた。
まぶしい日差しが、開いたドアの隙間から小屋の中に差し込んできた。鷺沼は、その光に目を細めながら、ゆっくりと立ち上がった。
外に出ると、先ほどまでの陰鬱な空気は消え去り、穏やかな風が吹いていた。まるで、長い悪夢から解放されたような、そんな清々しい気分だった。
空を見上げると、青い空には白い雲がゆっくりと流れている。先ほどまで、あのように恐ろしい体験をしていたのが、まるで嘘のようだった。
業深の影、残された感情
ドリームランドでの取材を通して、鷺沼は単なる幽霊の噂話では済まされない、深い悲しみと怨念のようなものを感じた。この場所には、過去の悲劇によって傷つき、今も彷徨い続ける子供たちの魂が残されていたのだ。
そして、その人々の負の感情すらも、黒田「業深」は金儲けの道具にしようとしているのだろうか。曰く付きの物件であることを隠して売りつけたり、心霊現象を利用して客を呼び込んだり…。
彼の悪行は、底なし沼のように深いのかもしれない。
帰りの車の中で、鷺沼は今回の取材で得た情報を整理し始めた。業務日誌の記述、聞こえてきた子供たちの声、そしてあのブリキの人形…。
それらは全て、この廃墟遊園地で過去に起こった悲しい出来事を物語っているようだった。
今回の記事では、単なる幽霊騒動としてではなく、この場所に残された子供たちの悲しみや、それを食い物にしようとする黒田の悪行についても触れるべきだろう。読者に真実を伝えることこそが、ライターである自分の使命だと、鷺沼は改めて感じていた。
しかし、黒田との関係は、これで終わりではないだろう。曰く付きの物件を専門に扱う彼と、それを取材する鷺沼。
二人の間には、これからも様々な形で因縁が生まれてくるに違いない。
悪夢の終焉、そして新たな序章
車窓から見えるドリームランドの廃墟は、夕日に照らされ、どこか物悲しいシルエットを描いていた。今回の取材で体験した恐怖と悲しみは、鷺沼の心に深く刻まれ、容易に忘れ去ることはないだろう。
彼は、今回の記事を通して、この遊園地で起こった悲劇を人々に伝え、二度とこのような悲劇が繰り返されないように警鐘を鳴らしたいと考えていた。
そして、人々の心の傷を弄ぶような、黒田のような悪徳業者の存在も、白日の下に晒さなければならない。
鷺沼探偵の、曰く付き物件を巡る取材は、まだまだ終わりそうにない。
そして、悪徳不動産屋「業深」との因縁も、深く、そして複雑に絡み合っていくのだろう。
今回の廃墟遊園地の悪夢は、彼にとって、数多くの悪夢のほんの序章に過ぎないのかもしれない。

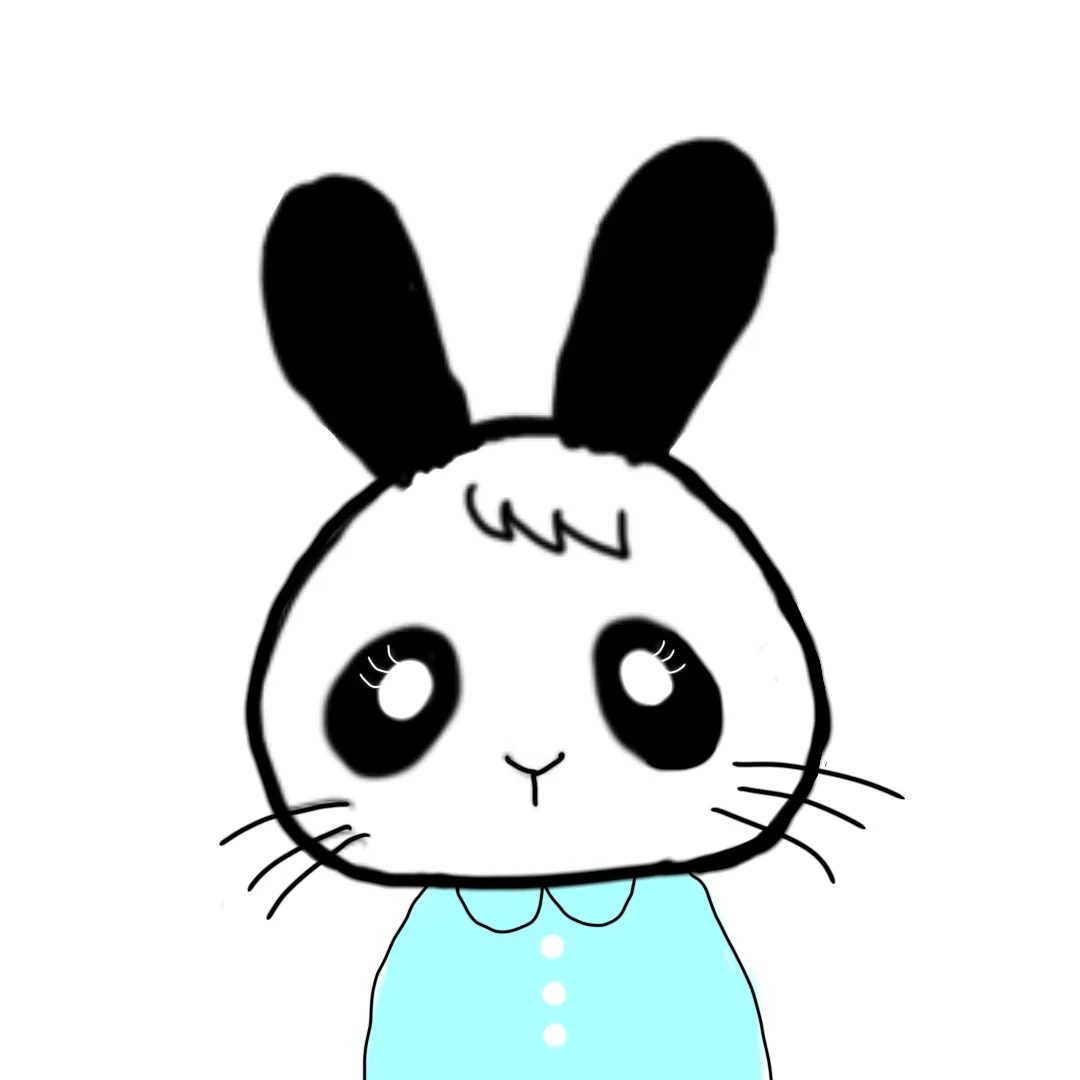

コメント